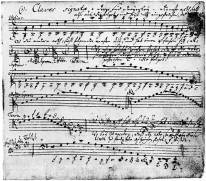
子どものピアノ教育について
* 現在改稿中のため、記述に不連続なところやむらがあります。(2009年9月7日)
1 ピアノ教育は音楽教育、音楽教育は人間教育
ピアノのレッスンは、「ピアノ演奏技術のレッスン」だけで成り立つものではなく、音楽教育の一環として行われるとき、はじめて意味をもつものです。そして、より広い見地に立つならば、音楽も手段であって、その目的は人間らしく生きることです。ですから、ピアノレッスンの根本的な原理は人間教育の原理であるといえます。
子どものピアノ教育の現況を見聞きして改良の余地があると思うのは、
①ピアノを習う子どものほとんどはピアノを職業とするわけでない。にもかかわらず、「ピアノの前で指はまわるが、ピアノ以外のことは何も知らない」人間を作り出すかのようなカリキュラムが組まれている。まず第一に、ピアノ以外の音楽もピアノに関係があることを教えなければならない。第二に、ピアノを職業としなくてもピアノを習ったことが人生を豊かにしたと感じられるようなレッスンでないといけない。
②音楽の世界はどんどん変化しているのに、音楽教育の基本的な考えがいまだに19世紀の西洋音楽に立脚している。一方で子どもたちが普段耳にする音楽は20世紀に興隆したポピュラー音楽や世界各地の民族音楽が多く、それらを通じて20世紀の芸術音楽の影響も受けている。レッスンの音楽と日常の音楽とが別物になってしまっている。現代の音楽と古典とのバランスを考え直さねばならない。
③受信と発信のバランスも考え直さねばならない。楽譜を読んだり演奏技術を身につけたりすることに比べて、作曲が軽視されている。本格的な作曲を全ての生徒に教える必要はないと思うが、せめてハッピーバースデイや童謡や簡単なポップス、テレビや映画の音楽なら、自分で聴きとって簡単なものでよいのでアレンジできるようになってほしい。
④教え方を現代化しなくてはならない。身体的な訓練においても、知的な訓練においても、19世紀の伝統といえる強圧的で機械的な反復練習に代わって、合理的で生徒の自発性を引き出すやり方が、20世紀後半にスポーツの世界でも勉強の世界でも工夫されている。また心理面での教育テクニックの進展も著しい。ピアノの教え方においてもその成果をとりいれなければならない。
という点です。
2 子どもの成長過程とレッスンのあり方
子供は大人とは違った感じ方、考え方をもっています。また、大人にとってよいことが子どもにとってよいともかぎりません。子どもに接するためには、子どものあり方を知ろうと努力しなければなりません。
子どもの成長のあり方についてはいろいろな考え方がありますが、私が特に参考にしているのは、ドイツの哲学者シュタイナー(1861-1925)の考え方です。
生まれたばかりの子どもは、肉体が母親から離れただけで、感覚、感情、思考はまだ目覚めていません。できれば出産予定日近くまで胎内で育って出産するのが望ましいように、感覚、感情、思考もふさわしい時期を待って目覚めさせねばなりません。
シュタイナーによれば6,7歳までは身体を保つ力(気力)を育てる期間です。歯がはえかわるのが、この時期が終了したひとつの目安とされます。伝統的な日本語では身体を保つ力を気と言います。元気、病気、気がつく、気になるなど、「気」を使ったさまざまな言い方を考えてみると、何となく気というもののイメージがつかめると思います(ちなみにヨーロッパで「気」にあたる言葉はエーテルで、シュタイナーもエーテル体という言い方をしています)。気力という言葉からわかるように、6,7歳までにつちかった身体保持力が、大人になってから意志を支えるものになります。
6、7歳から12〜14歳ぐらいまでの時期、だいたい小学校に通う時期は、自分独自の感覚、感情が形成される時期です。乳幼児期には親や周りの人の感覚、感情と自分自身のそれとが一体になっていたのが、小学校を卒業して中学生になる頃には、親や周りの人とは独立した感性・感情をもった人間として自分を意識するようになります。また、この時期は記憶力を伸ばす時期でもあります。
14〜20歳ぐらいの時期は思考力を育てる時期です。親や周りの人の言うとおりに行動するのではなく、自分で自分の人生をどうしたいか考えて行動することができます。
上のような考え方にたつと、いわゆる早期教育について、たとえ優れた指導方法であっても時期尚早な訓練は有害なものになりかねないということになります。例えば身体形成の時期である就学期以前に記憶力の訓練をしすぎると、身体形成のために使うべきエネルギーがそのために使われてしまって、結果として基礎体力をつける機会を永遠に失ってしまうということになります。基礎体力が弱いということは、無気力さにもつながります。いわゆる神童がある時期から急に無気力に陥る例は結構多いのではないでしょうか?同様に、感覚感情育成の時期である小学校時代に知的な訓練(例えば、受験勉強のように体験ではなく言葉や画像だけで覚える勉強)のみに偏ると、感情の深みを失いがちになります。感情が充分に育っていないうちに判断することに慣れると、表面的なものの見方しかできない鈍感な人間になる危険性があります。
逆に、時期にあった指導は効果的であるばかりでなく、有益です。小学校時代に記憶力の訓練をしたり、高校時代に自分の力で考えさせることは人間的成長を促します。
実際の発達には個人差があって割りきれないことも多いですが、上記を参考にして年令にふさわしいピアノレッスンのあり方を考えてみましょう。
(2年生ぐらいまでのレッスン内容)
就学前〜小学校1、2年生の時期は身体の根本をつくる時期です。この時期に身体の要求を第一にしてのびのび育つことが「生きる意志」の礎となります。レッスンが子供にとって「愛され保護されている」時間と感じられるように心がけます。
音楽を演奏するための体作り、楽器の扱い方や椅子のすわり方、音作り、聴音など基礎的な事柄を、いっしょに遊びながら身につけさせます。
(小学校の中学年・高学年のレッスン)
小学校の中学年から高学年にかけては感覚的、感情的に多くのことを学びます。また、記憶力を養うにも良い時期です。この時期に音楽を学ぶことは、感覚的、感情的に満足をもたらすだけではありません。音楽を通して秩序の感覚も学ぶことができます。楽譜を使う西洋音楽では知的な記憶力も養うことができます。この時期、楽譜を読むことにかなり時間をかけます。また、簡単な音楽史、楽典の知識も学びます。
(中学、高校生以上のレッスン)
この年代の生徒たちが必要とするのは、普段は口を出さないけれど困ったときには信頼して相談できる人です。人間的には対等の立場で、音楽においては専門家として助言します。
3 時代に即したカリキュラム
20世紀後半の日本では、ピアノのレッスンと言えば、バイエル、チェルニー、ブルグミュラー、ソナチネなど定番(ただし、日本のみの定番)の教材に即して行われるのが主流でした。(なぜバイエルが日本で生き残ったかについてはこちらをクリックしてください。)
これらの教材は19世紀の中頃に制作されたもので、18世紀末から19世紀初頭のヨーロッパ音楽を習得目標にしています。それ以前は宮廷や教会の音楽家が、貴族やお金持ちの子弟、音楽の才能の目立つ子たちにレッスンをするだけだったので、教材はたいがい手書きで、先生の自作や有名な作曲家の曲を五線ノートに書きこんでいくというスタイルでした。(下はバッハが長男のために作った音楽ノート)
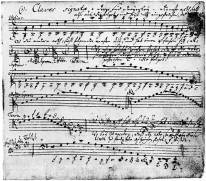
フランス革命を経て、市民層にピアノレッスンが広がると教師の不足が問題になり、「教師に力量がなくても、あるいは独学でも使える」教材として機械的な練習に重点をおいた練習曲集が数多く出版されました。バイエルなどはその流れにあります。19世紀末にいたって機会的なメソッドに対する批判が高まり、「本を読みながらでもいいからなるべく長時間練習するのがよい」という考え方から「工夫された練習法で集中すれば短時間でより高い効果が得られる」という考え方に変わってきました。
バイエルやチェルニーが制作された19世紀の中頃から150年以上の年月を経て、音楽の姿は変化しました。特に20世紀後半以降のピアノ音楽の世界の特徴は多様化です。大量印刷された教材による画一的なカリキュラムから、ふたたび手作り的な「ひとりにひとつのカリキュラム」の時代に戻ってきたように思います。
現代的なカリキュラムを組むにあたって留意したい点は以下のとおりです。
*従来なおざりにされがちだった発信型の内容(作曲、編曲、即興演奏など)をとりいれること
*アンサンブルに積極的にとりくむこと(連弾、合奏、弾き語りなど)
*レパートリーを広げること
*音作りに時間をかけること
*楽典の現代化(長短音階以外の音階の知識、コードネームの知識)
具体的なカリキュラムについてはこちらをどうぞ(製作中)
4 教授法の工夫
4.1 気質の理解
レッスンを効果的に行うには、ひとりひとりの子供の気質を知ることが重要です。
気質とは性格のタイプのことです。ヨーロッパでは伝統的に4気質論ということが言われてきました。4気質論は、この世を成り立たせている固体(地)、液体(水)、気体(風)、熱(火)という4つの物質(これを4大元素と呼びます)のうち、どの要素がその人のなかで優勢かで特定の気質が現れるという考え方です。(現代の一般的な理解では、熱は物質ではありませんが、古代ヨーロッパでは熱を4大元素の1つと考えました。熱のイメージとしては、興奮して熱くなってくるときに感じるような熱を考えるとよいでしょう)
参考までに図にまとめてみます。
| 名称 | 優勢な要素 | 長所 | 短所 |
| 胆汁質(火の人) | 火(熱) | 正義感が強く、不屈の意志を持つ | 短気で頑固、乱暴 |
| 多血質(風の人) | 風(気体) | 友好的で、好奇心が強い | 気が散りやすく、八方美人 |
| 粘液質(水の人) | 水(液体) | 粘り強く、穏やかな性格 | 怠惰、無関心 |
| 憂鬱質(地の人) | 地(固体) | 他人の苦痛への共感、考え深さ | 閉じこもり、けち |
胆汁質は火の人で、熱気にあふれています。困難に打ち勝つことがよろこびで、英雄タイプといえるでしょう。その反面、怒りっぽく、他人に厳しいことからトラブルメーカーにもなりやすいタイプです。
多血質は風の人で、軽やかで好奇心いっぱいです。明るく社交的で誰からも好かれそうですが、気が変わりやすく、約束を忘れたり、八方美人で結果として人を傷つけることがあります。
粘液質は水の人で、動きが緩やかですが底深い持続力があります。穏やかな性格で誰からも好かれそうですが、寝ることと食べること、休むことが好きなので、時として怠惰になります。
憂鬱質は地の人で、冷静できちっとしています。ものごとを深く考えますが、悲観的になったり、批判的になったりしがちです。
指導にあたっては、「相手の気質を尊重し、その長所を引き出す」ということが重要です。
例えば、先生が胆汁質で生徒が多血質であるとしましょう。生徒は多血質らしく次から次へと目移りしていますが、先生は「思い込んだらその道を突き進む」胆汁質なので、生徒の落ち着きのなさが我慢なりません。しかしそれで「少しは落ち着け!」と怒るというのは、、犬が猫にむかって「犬のようになれ」と説教しているようなもので、根本に無理があります。先生の立場の人間は相手の気質を見抜いて、「まずは自分が想像上でその気質になってみて生徒の行動を見る」という作業ができなくてはなりません。そうすれば、「気が散りやすい」という欠点も、「多くのものを愛する広い心」に育てていけばいいのでは、と考え直すことができます。
指導法は基本的に「同種の原理」によります。「胆汁質」の子どもには、胆汁質的に短くはっきり確固とした原則を示します。「多血質」の子どもには、多血質的に楽しく新しい話題をどんどん提供します。「粘液質」の子どもとは、ゆっくりマイペースでレッスンをすすめます。「憂鬱質」の子どもには、やさしい問いかけで試行錯誤を促し、発見の喜びを共有します。気質のバランスをとろうとして、子どもの気質と反対のやり方をすることは逆効果です。